大切な家族を亡くしたときの不思議な感覚。
「かなしいけど、さみしくない」
…について、綴ります。
死別で沸き上がるさまざまな感情
死別の時に湧き上がる感情はさまざまだと言われます。
悲しい、寂しい、辛い、苦しい、憎い、信じられない、あってはならない、あるはずがない…。
後悔、罪悪感、事実の否認、懺悔、憎しみ、敵意など。
あらゆる感情が、自分の中から湧き上がり、外からこちらに押し寄せます。
こうやって感情をことばに置き換えられるのはまだマシなほうで、そもそも現状認識ができず、うまくことばにできず、パニックに陥るという人も、たくさんいます。
そんなはずはない。でも死んだ。いや、そんなはずはない。でも死んだ。だけど…。
現実とその否認のくり返しが、パニックを増長させるんです。これが、本当に辛くて、とても苦しい。
母の危篤を伝えてきたのは、父でした。
電話越しの父は、突然のことに、パニックを起こしていました。
母の危篤とともにぼくが驚いたのは、これまでに聞いたことのない父の悲痛な声に、でした。
五重塔への誓い
京都駅のホームに、新大阪行きのこだまが入ってきました。
次にやってくるのは博多行ののぞみ。
どうせ新大阪で乗り換えなければならなかったので、次ののぞみに乗ればよかったものの、少しでも早く家族のいる山口に近づきたかったぼくは、目の前のこだまに乗車しました。
車窓から見えるのは、東寺の五重塔。
ぼくにとって東寺は少し特別な場所で、というのも、晩年の母が弘法大師空海を信仰していて、その空海が建てたのが東寺です。東寺は母にとっての聖地であり、五重塔は聖地にそびえるシンボルだったわけです。
昼間にお参りするつもりだった東寺。もしもぼくがお参りして観音経を読んでいたら、きっと母は助かっていたかもしれない。そんな想いが拭いきれずにいました。
その時のことは、こちらの記事に詳しく書いています。
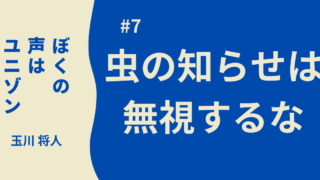
ぼくは、その五重塔に向かって、強烈に祈っていたのですが、でもその祈りは、願いごとなんかではなく、真理の確認と、誓いのようなものでした。
つまり…
「諸行は無常。だれだっていつか死ぬ。いま、母にその時がやってきたのだ」という真理に触れ、「この流れに身を任せます。これからのぼくを、どうか見守って下さい」と誓う、こんな感じだったのです。
不思議にも「母を助けてほしい」とは思わなかったのです。どんなに人間が願って、努力しても、抗うことのできない大きな力があるのだということを、ビンビンに感じていました。
それは同時に、大きな力に対峙する人間の小ささを知らされた瞬間でもありました。祈りや帰依って、きっとこういう瞬間に生まれるものなのでしょう。
新幹線が西に進むに連れて、五重塔はどんどん小さくなります。薄暗がりの中に消えていく五重塔を、ぼくはデッキの窓からずっとずっと見つめていたのです。
新大阪で乗り換えののぞみを待っている時に、兄から電話がありました。
母の訃報でした。
なんで笑っちょん?
20年も前のことなので、記憶が結構あいまいです。
葬儀場に横たわる母が、布団の上だったか、棺の中だったか、はっきり覚えていません。
ただ、葬儀社による化粧がひどかったのは、よく覚えています。過剰なおしろいと口紅。そもそも紅をさすような人ではありませんでした。
ただ、そのひどさというのは、のちに葬儀社で働くようになってから分かったのであって、この時は「まあ、こういうものなのか」と、違和感をそっと自分の中に押し込めました。
葬儀の時の記憶は、ほとんどなく、限りなく断片的です。それは、当時の自分が決して冷静ではなかったことを示しているのかもしれません。
父が、兄が、どのような言動をしたのか、そのほとんどを思い出せずにいます。
ただ一瞬、ぼくは横たわる母の前で、ふっとほほえみました。自分の中に、あたたかい何かがかすかにこみ上げた感覚を覚えています。
もしかしたらそれが、母がぼくの中に入り込んできた瞬間だったのかもしれません。
でも、その直後、ぼくのほほえみを見た兄は「なんで笑っちょるん?」と、非難を帯びた目で見てきました。
死別は、悲しさや淋しさだけでない、いろんな感情がうごめく現場です。ほほえみも、非難も、笑いも、罵りも、人のあらゆる感情が発露します。
ぼくはほほえみ、兄は怒っていた。
血を分けた兄弟であっても、母の死への受け止め方は、大きく異なっていたのです。
ぼくを号泣させたもの
自分は冷静だ。
その自覚もまた、母の突然の死に対するぼくなりのディフェンス反応だったのかもしれません。
「諸行は無常。だれだっていつか死ぬ」などと達観のふりをしつつ、その中に悲しみを押し込めていたのかもしれません。
そんなぼくを激しく号泣させたのは、通夜の時の僧侶の読経です。
低く鳴り響くおごそかな鏧子の音。そして、独特の抑揚で放たれるお経の一語一語が、低く、野太く、はらわたに響いたのです。
頭による理解をはるか超えて、身体中の堰という堰が外れ、涙がとめどなくあふれ出ました。
もう周囲の目も、恥もなく、あふれるままに涙を出そうと、とにかく泣きました。
この時の読経は、いまも時々思い出されます。
普段の法事なら眠気を誘うあのお経が、亡き人に向けられると、こうもこちらの感覚を揺さぶって来るのかと、そのことに驚きました。
「無力のぼくは、母の供養と成仏をこのお坊さんに任せるしかない」
そんな想いで、目を閉じ、涙をぬぐうことなく、読経に耳を傾け、手をずっと合わせていたのです。
かなしくけど、さみしくない
ぼくの声はユニゾン。亡き人とともにいます。
はじめてこの感覚を覚えたのが、母との死別の時だったのです。
それが、東寺を見た時なのか、ふとほほえんでしまった時なのか、通夜の読経に揺さぶられた時なのかは、はっきりと思い出せません。
でも、通夜の読経で号泣している時、すでに母はぼくの中にいました。それだけはよく覚えています。
ぼくの涙は母の涙でもありました。
「辛いね、悲しいね。一緒に泣こうね」みたいなことを語り合っていたのを覚えているんです。
そしてこうも言い合いました。
「一緒にいるから、さみしくはないね」
かなしいけど、さみしくない。
一緒にいるから救われるわけじゃありません。でも、一緒にいるから、さみしくはありません。
一緒にいる。実はそれだけで、充分に救われているのかもしれません。
ぼくの声はユニゾン
ぼくの中には、亡き父、母、兄、祖父母、たくさんの死者やご先祖さまがいます。
ぼくの放つ声は、亡き人たちの声が重なり合うユニゾンです。
キーボードを叩くぼくの指先にも、死者や先祖の存在を感じます。
そんなぼくが、佐々井秀嶺師からいただいたこのことばを寄る辺にして、
日々感じたこと、考えたことを綴ります。
あなたが本を書きなさい。
ここにいる人たちの力を借りて
ここにいる人たちのために
本を書きなさい。
あなたの力を借りて、あなたのために、ことばを綴ります。
今日という日が、あなたにとってよい日となりますように。
そして、ここに綴ったことばの一つひとつが、
あなたの幸せのお役に立てますように。




コメント