ぼくは母の通夜でずっと泣いていた。それはもう、まわりが引くくらいに。
でもそれは、寂しいとか、悲しいとか、そういった次元ものではなかった。
肚の奥底が震えて、それが涙となって目から噴き出した、そんな感じだった。
そしてその涙を引き出した若僧の読経。
あの日を境に、ぼくの声はユニゾンになったのだ。
涙のトリガー
祖父が亡くなって一か月も経たないうちに、次は母が亡くなった。53歳で亡くなった母の通夜にやってきたのは、30歳前後の若い僧侶だった。
急死した母の葬儀はカオスで、家族や親戚以外にも、地域の人、お店のお客さん、兄の友人や仕事関係者など、たくさんの人が出入りしていたのをぼんやりと覚えている。記憶があいまいなのだ。
そんな中で誰かが放ったことばが、いまでも頭の内側にへばりついている。
「故人の半分しか生きちょらんのに、ちゃんと供養できるんかいの」
こんな皮肉めいたことばが出たのも、だれもが冷静でいられなかったからだろうし、ぼくも「たしかにそうだよな」と思った。
ところが、その不安は杞憂に過ぎなかった。
僧侶は、しっかりとした足取りで畳の上を進む。そのたびに衣が摺れる音が静寂の中に響き、参列者たちの間をすり抜けるように祭壇の前へ向かっていった。
まだ若いながらも、彼の姿にはどこか凛とした佇まいがあり、修行を経て培われた強さを感じさせた。机の上に荷物をそっと置き、数珠を手にかけると、深々と合掌し、母に対して丁寧に一礼する。
数週間前に祖父の葬儀に出席したばかりだったが、僧侶という存在をここまでじっくりと見つめたのは、これが初めてだったかもしれない。その後ろ姿は、まるで時間が止まったかのようにぼくの目を釘付けにしていた。
通夜の儀式に入る前、僧侶は最前列に座るぼくたち遺族の方を向き、穏やかながらも力強い声で一言だけ告げた。
「心を込めて、お勤めさせていただきます」
その語り口は、まるで一つ一つの言葉をかみしめるかのように重みがあり、悲しみや戸惑いで揺れるぼくたちの心をしっかりと受け止めるようだった。彼の目はまっすぐにぼくたちを見据えており、目じりのやさしい曲線がその人柄を表しているようだったが、その奥には誠実で鋭い眼差しが宿り、どこか安心感を与えるものがあった。
やがて僧侶はゆっくりと正面を向き直り、香を焚くと、静かに鏧子を叩き、「ごおーん」という低く深い音を厳かに響かせた。その音はまるで波紋のように広がり、瞬時にぼくの肚の奥深くにまで響き渡った。
「やばい、泣きそう」
京都の下宿で危篤を告げられた時、新幹線の車窓から東寺に祈った時、新大阪の駅で訃報を聞いた時、母と対面した時ですら、涙は出なかった。ぼくはしっかりと、冷静に、現実を受け入れているつもりだったからだ。
なのに、この鏧子の太く低い音は、あらゆる堰を乗り越えてきた。
僧侶の読経が始まると、涙はすぐに噴き出た。何を語っているのか聞き取れない経文の、実直で誠実な音律と抑揚が、悲しみに沈む遺族全員の心を揺さぶり、魂を震動させた。
これまでも、数年に一回の法事に参加したことはあった。そこで知ったのは、お経は眠くなるものだ、ということ。
でも、この日はまったく違った。死者に手向けられる読経が、こうも身体の芯にまで沁み渡るとは思わなかった。
「このお経は信頼できる」と、直感した。
するともう、泣くしかなった。肚の底から涙が噴き出して仕方なかった。周りの人たちも若干引いていることは分かった。でも、抑え込むべきでないし、それでも抑えきれない涙。
肚の底からの響き。いまにして思うと「阿頼耶識の轟き」としか言いようがない。
ぼくの中に母はいた。この涙は、ぼくの涙で、母の涙だったのだ。
2500年の力
30歳の若僧は、確実に53歳の母を供養したと、家族みんなが納得していた。
「お通夜の副住職、ぶちよかったね」
「そうそう、声もええし、力強かった」
「誠実な感じが、ぶちしたっちゃ」
葬儀を終えたあと、ぼくたち家族はこのように言い合った。
世間知らずの22歳だったぼくが、通夜の席で本能的に感じたのは、「伝統の力」だ。
たかだか30歳しか生きていない若者が、50代の苦労を知れと言っても、無理がある。
でも、2500年の伝統を背負った30歳は、伝統的な服装、儀式、身のこなしを通じて、53年の生涯をたしかに包み込んでくれた。
彼が所属しているのは臨済宗。日本で約800年の歴史がある。
読経を聞き、激しく泣きしながら、ぼくは想像した。
いまここで読まれているのと同じお経が、この国の、いろんな時代の、いろんな地域の、いろんな人たちの人生の最期に、手向けられたのだろう。同じ所作、同じ儀式、同じお経、同じ抑揚、同じ音律で。
伝統の力と僧侶の誠実さが、ぼくの阿頼耶識を刺激し、肚の底から涙を噴き出させたのだ。
2500年の、インドの、アジアの、日本の、幾千万の人々の記憶と、先祖の、母の、ぼくの記憶とがひとつに融け合って、涙となって、噴き出た。
あの涙は、ぼくのものであり、母のものでもあり、世界のものである。
あの日、ぼくは激しく泣いたが、母も、世界も、泣いていたのだ。
悲しいけど寂しくないという不思議な感覚。母がぼくの中に入り込んだのは、たぶんあの瞬間だったと思う。
あの瞬間から、ユニゾンが始まった。
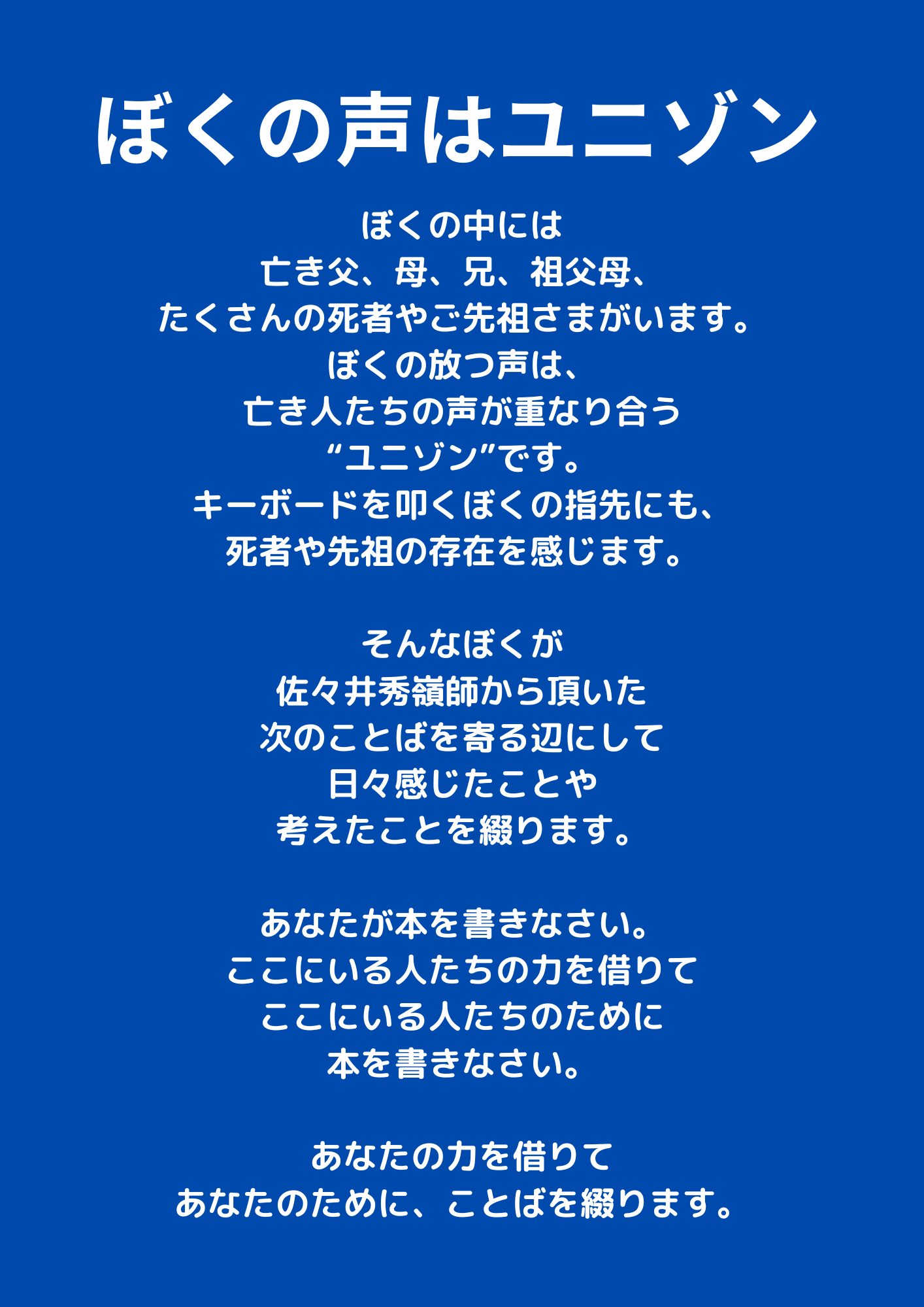

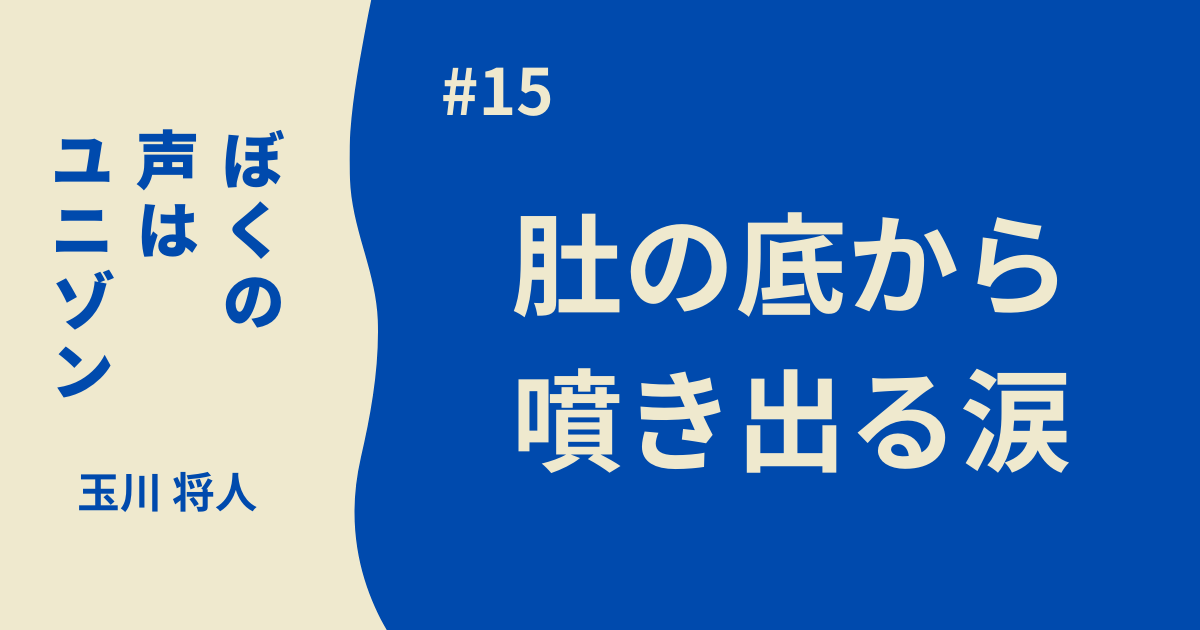

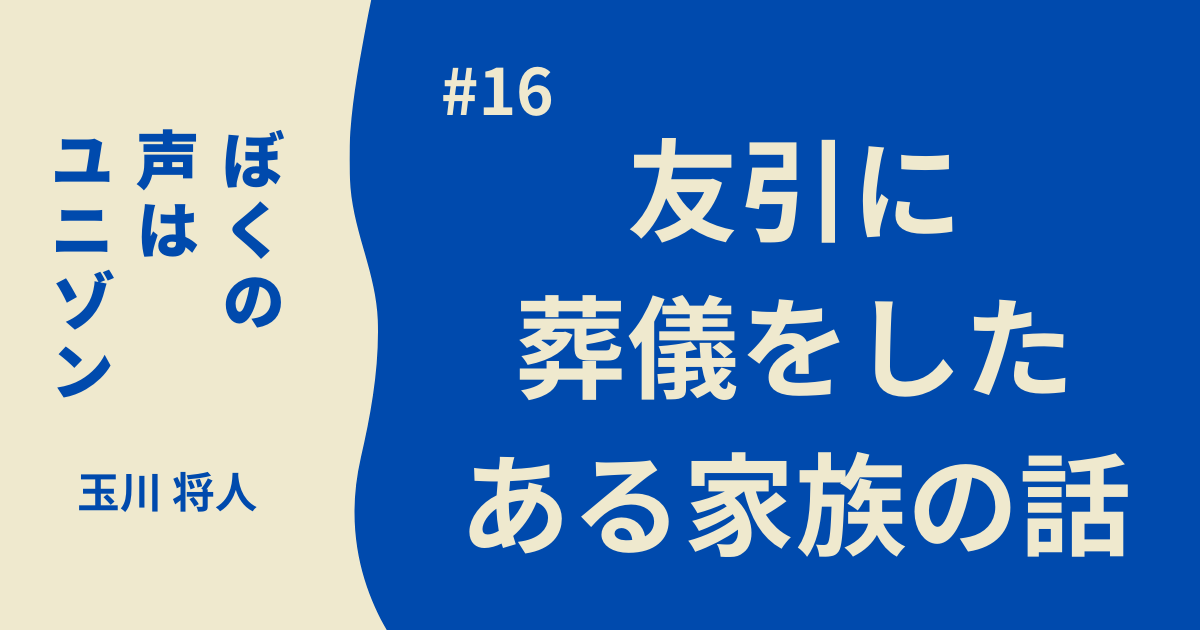
コメント