想いを通じ合わせるには、聴き方と伝え方の両方が大事ですが、それよりももっと大切なことがあるかもしれません。
今日は、伝えることを仕事とするお坊さんとのやり取りの中で感じたことを綴ります。
壁打ち&言語化担当のぼく
ぼくは、お寺探しのポータルサイト『まいてら』で、コンテンツ作りのお手伝いをしています。
お坊さんの頭の中を聴かせてもらって、それを一緒にことばにしていく。ぼくは壁打ち相手、ということですね。
なにかをアウトプットする時、多くの方は、イベントや取り組み、そのストーリーや実績などを軸にことばを紡いでいきます。つまり、伝えたい「何か」があるんですね。
そんな中で、妙華寺の中川和則住職は、「伝えることのむずかしさを伝えたい」と言ってこられました。何かを伝えるのではなく、伝えることそのものに対しての思索、ということです。
自問自答のコンテンツ化はむずかしいのかなと思いつつ、その壁打ち相手として、精一杯ことばを受け止め、考えました。そしてこちらからもことばを返し、対話を深めていく中で、記事はひとつの結論へと導かれていきました。それは、
「伝えることよりも聴くこと。聴くことよりも一緒にいることが大事では?」
…ということです。これは、ぼくにとっても大きな気づきでした。
詳しくは、こちらの記事をご覧いただきたい!

世界は「伝える」であふれている
中川さんとのやりとりを通じて、ぼくはこう考えました。
「あれ? すべての人間が伝えることのむずかしさに苦しんでるんじゃね?」
…ということ。
お坊さんの仕事は、布教や伝道、つまり仏法を人々に伝えることです。
でも、よくよく考えたら、お坊さんに限らず、ぼくたちの暮らしや仕事にも、「伝える」はたくさんあふれています。
片思いの相手への告白も、職場での人間関係(上司の指示、部下の報告)も、家の中での会話も、新商品のプレゼンも、政治家の選挙公約も、みんなみんな、伝えたいなにかがあり、それがうまく伝わると嬉しいし、伝わらないと苦しい。
文章を書くとはだれかにことばを伝えることだし、仏壇を売る時も商品の魅力やお店のよさをお伝えしています。
どうやら、この世界は「伝える」であふれているようです。
聴くことの重要性
こちらの想いがうまく伝わる、伝わらないの分水嶺は、相手の気持ちが分かっているかどうか、にあります。
その人が頭の中で理解でき、心に刺さることばで伝える方が、想いはより伝わりますもんね。
相手の頭の中と心の中を知る最上の方法として「聴く」ことの重要性があちこちで叫ばれています。
ここ最近、傾聴がとってもブームです。
『聞く力』とか『人は聞き方が9割』とか、『LISTEN』とか、ベストセラーには軒並み聴き方のノウハウ本。
ビジネス書を開いてみても、顧客の、ユーザーの、部下の、上司の、仲間の、家族の声を聴くことの大切さが必ずやと言っていいほど説かれています。
聴き上手は人から好かれますし、聴く力があると相手はこちらに心を開いてくれる。恋愛にビジネスに、傾聴力は目標の達成に大いに役立ちます。
相手が何を望んでいるかを知るためにも、相手がこちらに信頼を寄せてくれるためにも、聴くという姿勢は必要不可欠です。
相手の声をしっかり聴き、想いを汲み取った先にこそ、伝えるべきことば、伝えられる関係性というものが生まれてくるのですから。
聴きすぎることの違和感
一方で、聴きすぎることの違和感を、感じたりします。
というのも、ぼくは仕事柄、日常的にインタビューをしまくってます。
記事化を前提としたインタビューももちろんですが、職場や家庭やいろんな場所で聴き役にまわることが多く、それはそれで、それなりに役に立っているのかなと思っています。
聴くこと自体はすばらしいスキルである反面、これもやりすぎるとおかしなことになってしまうんです。
「聴くぞ聴くぞ!」と思って相手と会話していると、「わたしは聴き役、あなたは答える役」という風にポジションが固定されちゃって、会話がナチュラルじゃなくなってしまいます。
また、根掘り葉掘り聞かれることを嫌がる人だっています。
インタビューって、聴かれる側に「これからインタビューを受けるぞ」っていうスイッチが入るからまだいいものの、そうじゃない場合、「なんでこんなにあれこれ聞いてくるの」、と不審に思う人もいることでしょう。
もっと言うならば、そもそも話すのが苦手、聴くのが苦手、コミュ全般が苦手って人もいますよね。こうした場合、「聴く=話す」という前提が成り立ちません。
一緒にいるだけで、充分
だから究極は、同じ時間、同じ空間を一緒に過ごす。まずはこれだけで充分じゃないかと思います
何を考えているか全くわからないけど、ひとつ屋根の下でずっと一緒に暮らしているという家族もいるでしょうし、伝えたいことがうまく伝わらないけど、同じ職場でずっと一緒に働いている同僚だっている。
『スラムダンク』の桜木と流川って、めっちゃ仲悪いじゃないですか。
でも、ずっと同じバスケ部で、同じ時間と空間をイヤというほど一緒に過ごして、同じ方向を向いている。そういう間柄の中で、伝わるものもあるのではないかと。
お寺の場合、お坊さんのことばが伝わらなくても、お檀家さんの話を上手に聴くことができなくても、お寺に定期的にお参りしてもらうことでしみ込むように伝わる仏法というのも、またあるのではないかと思うのです。(『まいてら』の中で中川さんはずばりそのことを語ってくださった!)
一緒にい続けていた友だちが、気づいたら恋人になっていたり。
グループの中で声が小さくて、いっつも端っこにいるけれど、ずっと一緒にいることでなんとなく仲よくしてもらえるとか。
口下手で不器用だけど、いつもまじめに営業に来てくれるからこの人に注文しちゃうとか。
「一緒にいる」ことで伝わるものって、いろいろあると思うんです。
うまく想いが伝えられなくても、うまく話を聴けなくても、まずは同じ時間、同じ場所を共有する。その人を仲間として、自分の中に受け入れて、にこにこと、おだやかに接してみる。
その積み重ねが、相手を知ること(=聴く)に、そして自分を知ってもらうこと(=伝える)に、つながるような気がしています。
伝えることを仕事とする者として、大きな気づきをいただきました。
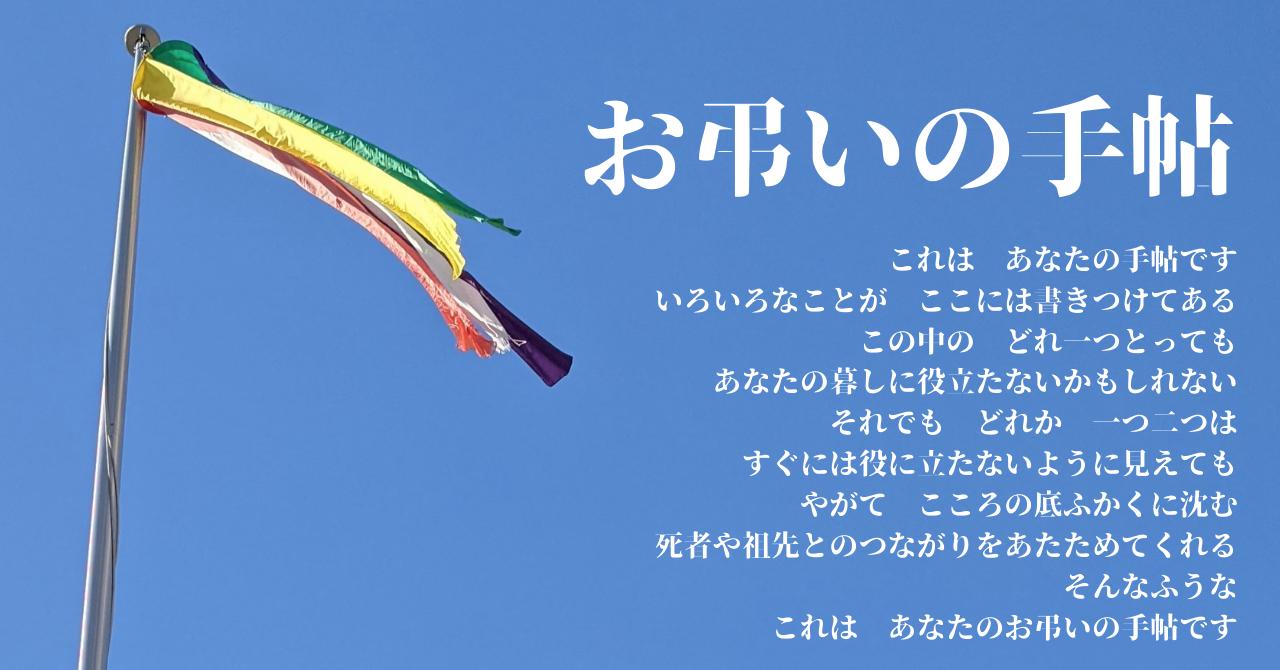
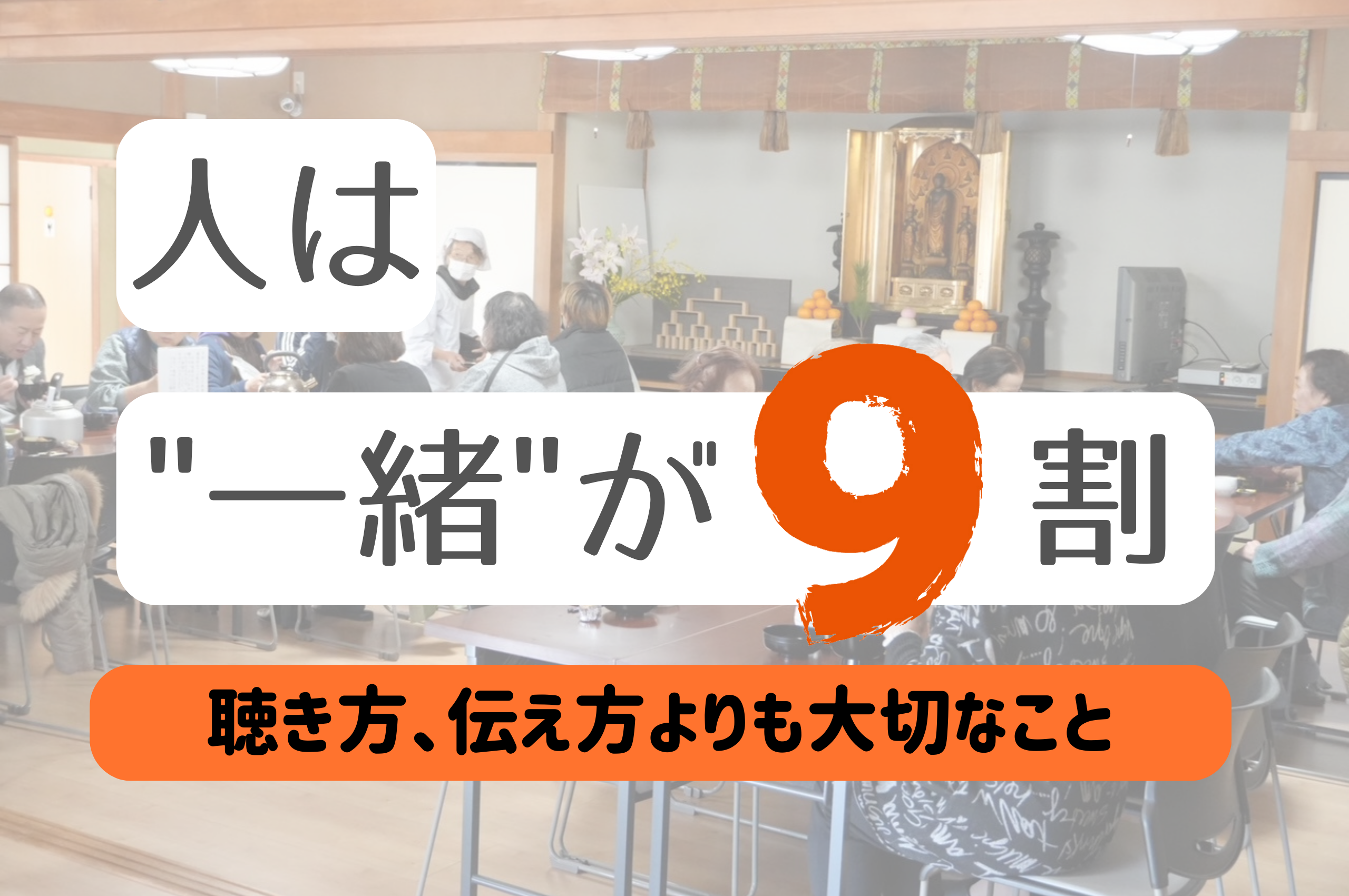
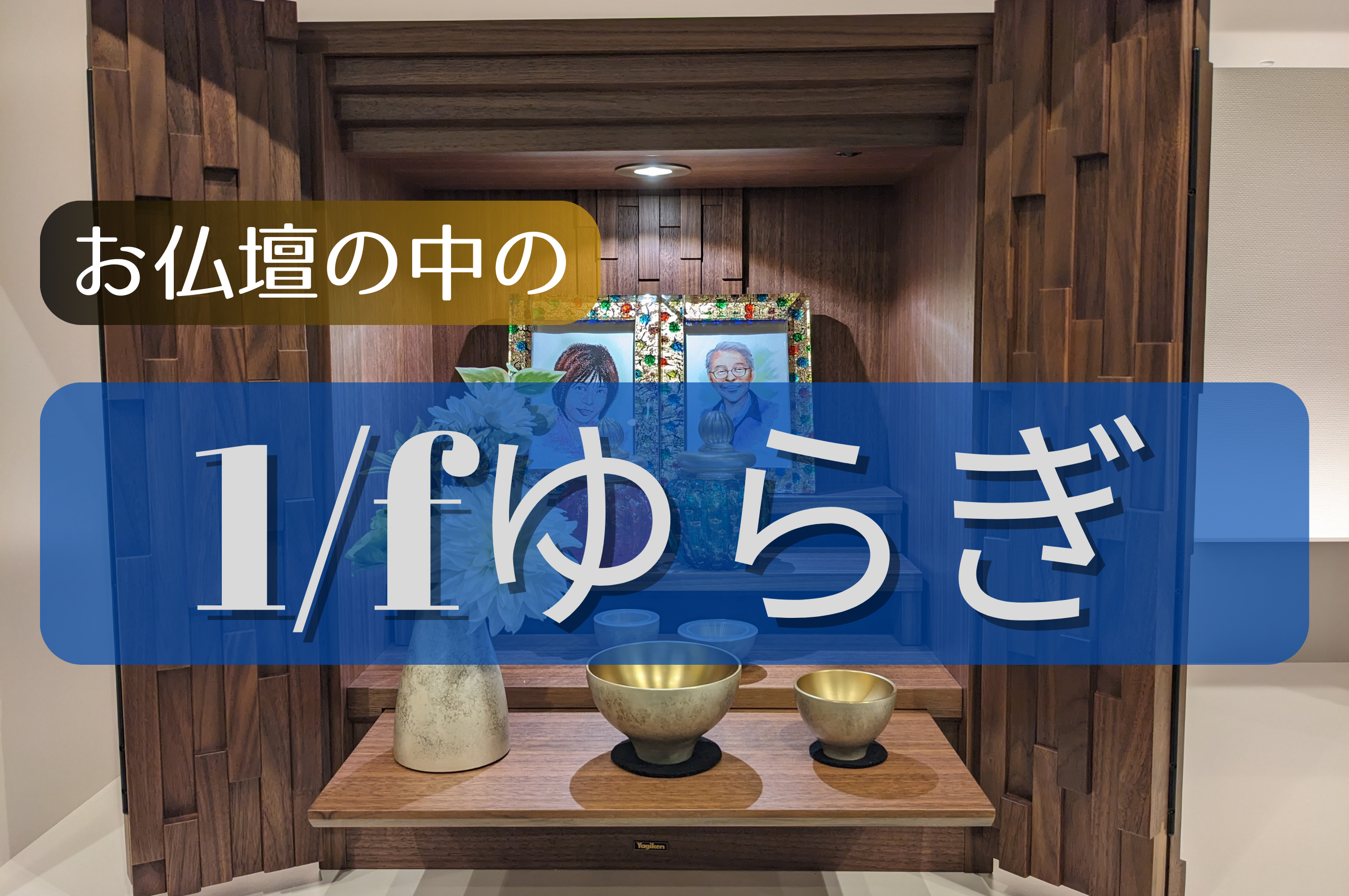
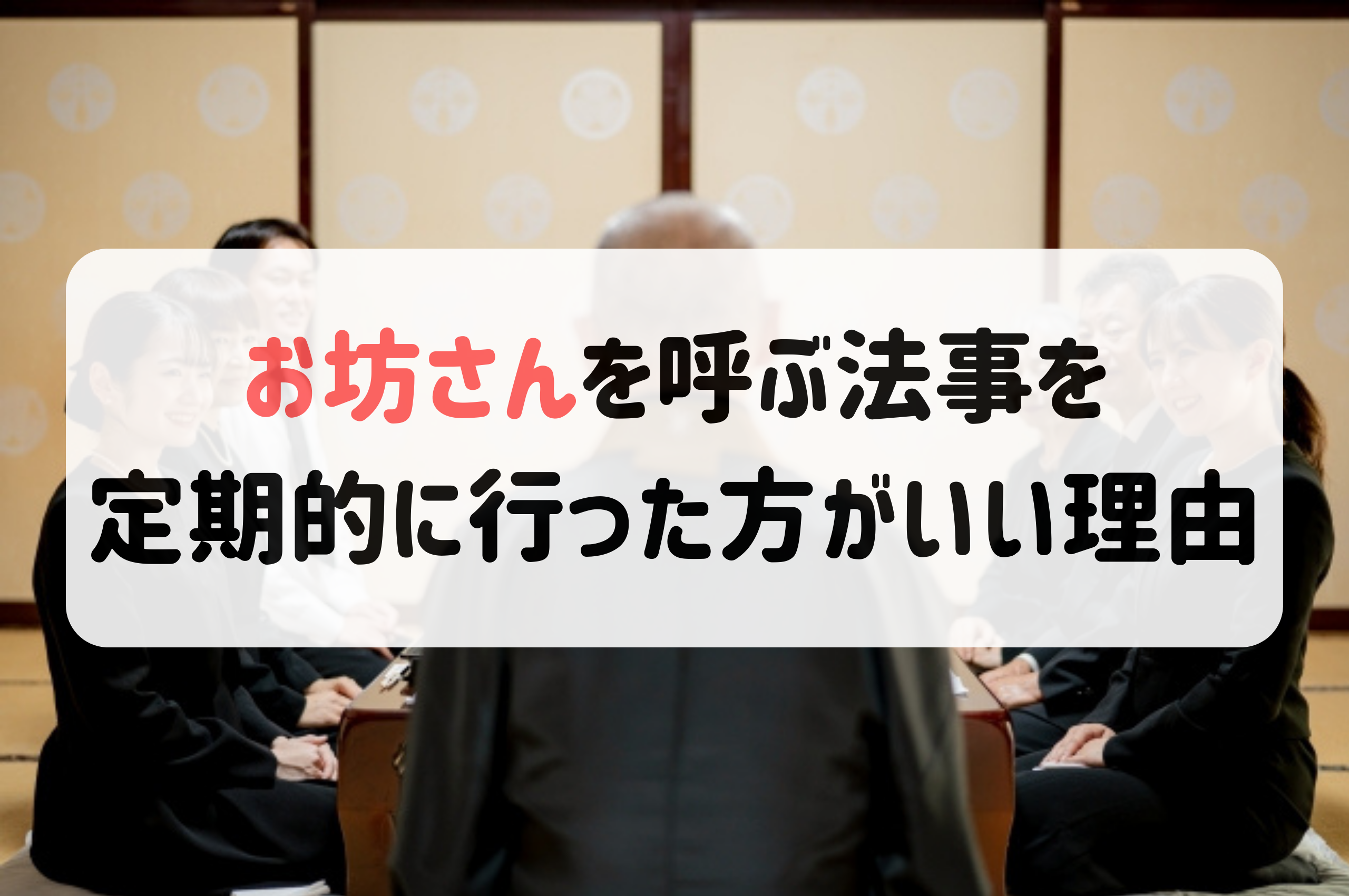
コメント