「虫の知らせ」とは、なんとなくよくないことが起きそうな予感のこと。
20代前半、ぼくは立て続けに家族を亡くしたが、その時の虫の知らせについて、綴ろうと思う。
おっくうな午後
ぼくが22歳になった2004年。1月21日に祖父が亡くなった。享年79。
祖父の葬儀は家族葬で営まれた。久しぶりに家族みんなが揃い、思い出話に花が咲いた。
身近な人ではじめての死。お葬式とは、こうも穏やかで、明るいものなのかと、少し驚きもしたが、酒をたしなみ始めたばかりのぼくは、日本酒を飲んでは、夜通し家族たちと話し込んだ。
「家族みんながこうして元気にやっちょる姿を、おじいちゃんもきっと喜んどるっちゃ。今年はええ年になりそうじゃね」
そのように語っていた母は、1か月も経たないうちにこの世を旅立った。享年53。
ぼくは祖父の葬儀を終えたあと、京都の下宿に戻っていた。家賃2万円の風呂なし共同トイレのアパートに、本と服とパソコンだけを持ち込んで、クリーニング屋でのバイト代、月8万円で生活していた。
金を稼ぐ力のないぼくが京都でできることと言ったら、読書と社寺巡り。
京都にはたくさんの古本屋があった。100円均一で世界中の古典文学が読めた。
そして京都には千年の歴史を超える社寺がたくさんあった。狸谷不動尊、伏見稲荷、東寺、下鴨神社、行きつけがいくつかあった。
その日は2月18日。寒さが続く中、珍しく日差しのあたたかい日だったのを覚えている。
真冬のクリーニング屋は閑散期で、その日も午前中で仕事を切り上げて、正午近くに安アパートに帰宅した。
18日と言えば観音さまの縁日。急遽昼から時間ができたので、午後をどのように過ごそうか。観音経を上げに東寺の大師堂に行こうかと悩んだものの、なんとなくおっくうだった。畳の上にゴロンとなり、一乗寺の萩書房という古本屋でまとめ買いした江戸川乱歩全集を読むことにした。
日当たりの悪い北東の角部屋。薄暗がりの中ページをめくっていると、ふと、
「そういえば、じいちゃんの四十九日はいつだっけ?」
…と思い至り、母に電話した。
しかし、電話はつながらず、留守番電話に切り替わった。ぼくはなにかメッセージを残して、再び乱歩を読み進めた。
夕方、父からの着信。珍しいなと思いつつ「もしもーし」と出てみると、いままでに聞いたことのないパニックに陥った父の悲壮な声。
「母ちゃんが、死にそうなんじゃ。風呂に溺れて、死にそうなんじゃ」
ぼくはすぐに京都駅に向かい、新幹線に飛び乗り、実家のある山口に向かった。
車窓からは東寺の五重塔が見えた。いつもの五重塔だ。
晩年の母はお大師さんを信仰していて、そのお大師さんが建てた東寺だ。今日お参りしていたかもしれない東寺だ。
その時、ぼくにある想いがよぎった。
「あの時、原付を走らせて、東寺にお参りしていたら、観音さまが母を助けていたかもしれない」
「あの時、ふと何気なく母に電話をしたのは、母からの何かを受け取っていたからかもしれない」
「あの時、生死の境で、母はぼくに向けて何かを叫んでいたのかもしれない」
新幹線が新大阪に着いたとき、兄から電話があった。「母ちゃん、死んだよ」
葬儀場に着き、母と対面し、死体検案書を見た。死亡推定時刻は正午ころだった。ぼくからの着信音は、母の耳に届いていたのだろうか。
母の葬儀の10日後に、祖父の四十九日と納骨を行った。ぼくは母の遺骨を抱えて、法事と納骨に参列した。
骨が骨を見送る。傍から見ると滑稽かもしれないが、やっている側は真剣だった。
渋谷の空 秋晴れ
母が息を引き取った半年後。ぼくと父は千葉と東京を旅行した。
母が亡くなった数か月後、父は脳梗塞を患った。大事には至らず、リハビリのおかげでなんとか復調し、仕事復帰する前に、慰安を兼ねてに関東に出向いたのだ。
千葉の成田は父方の古いルーツだった。最愛の妻を亡くした父がルーツを巡りたくなる心情は、42歳になったいまならよく分かる。
初日は成田山新勝寺を一緒にお参り。2日目は別行動。父は浅草と両国を散策し、ぼくは山手線に乗ってはじめての東京を満喫した。夕方には両国国技館で合流して、大相撲を観戦した。
9月14日。絶好の秋晴れ。宿のある浅草から銀座線で上野へ。そこから山手線外回りで渋谷に向かった。
90年代に10代を過ごしたぼくにとって渋谷は憧れの街だった。ピチカート・ファイブ。フリッパーズ・ギター。コーネリアスの世代である。音楽も、ファッションも、文学も、「渋谷系」であふれていた。
山手線の車窓から眺める景色をドキドキしながら眺め、たしか大崎を過ぎたあたりだった。携帯電話には兄からの着信。
さすがに田舎者が車内で電話をするのは憚れる。午前11時ごろに渋谷駅で降りて、眼前にはあのスクランブル交差点。その先には渋谷109。この感動を、兄に伝えたいと思った。
電話しても兄は出ない。逆に留守電が残されていたので再生した。このときのやさしい兄の声を、忘れない。
「おう。まーぼー。特に用事はないんやけどね。またね」
再び兄に電話してみた。兄は出ない。次はこちらから留守電を残した。
「兄ちゃん。じつはいま、東京に来とるんよ。父ちゃんの快気祝いと、先祖巡りしたいって言よったけえね。いま渋谷の交差点の目の前におる。空がぶちきれいで、人もぶちおるし、広告もぶちある。東京すごいわ。またお土産買って帰るけえね」
…みたいなことを無邪気に話した記憶がある。
その後、両国国技館で父と合流し、大相撲を観戦したあと、国技館前のちゃんこ屋で鍋を注文し、それを待っている時だった。
義姉から電話。「お兄ちゃん、亡くなったんよ」
ちゃんこをキャンセルして、宿に戻って、荷物をまとめて、東京駅までタクシーで走り、新幹線に乗車。終点の広島駅からタクシーで1時間半。時計の針は日付をまたいでいた。
葬儀場の布団に横たわる兄は穏やかな顔をしていた。
話を聞くと、帰らぬ人となったのは11時過ぎ。ぼくへの電話の直後だった。
こんなことってあるんか。痛恨だった。
虫の知らせを、またも受け取れないでいたことが悔やしかった。
虫の知らせを無視する
妻を亡くし、息子に先立たれた父は、すっかり弱ってしまった。ぼくは京都の下宿を引き払い、父の商売を手伝っていた。
でも、どうしても自分の人生を生きたい、都会で暮らしたいという自我を抑えきれなかった。
ある日の夜、ぼくは父に切り出した。
「東京で暮らしたいんじゃ」
父は反対しなかった。自分は自由にここまで人生を生きてきたのに、息子には不自由をさせていることへの負い目もあったのだろう。
「父ちゃんは大丈夫じゃけえ、お前の生きたいように生きろ」
それから、夜のバイトをし、お金を貯め、満を持して東京に引っ越した。
はじめて勤めたバイト先は古本屋。そこでいまの妻と出会う。彼女とはすぐに意気投合し、1か月後には付き合いだし、2か月後には結婚を決めた。
彼女は電話越しで父に
「いつか必ず山口に帰りますからね」
と話し、父も喜んでくれていた。
結婚するからにはバイトではだめだと、相手の両親にけじめをつける意味でも、ぼくは就職活動をした。行き先は、葬儀社と決めていた。
たまたまハローワークで引っかかった葬儀社に採用され、4月5日に入社初日を迎えた。
いきなり2件の遺体搬送。2件とも自宅での変死。大都会東京で、独居の高齢者はこういう形で息を引き取るのだ、そして遺体の収容は速やかに行われ、行政手続きを踏まれていくのだと、多死社会の生の現場をまざまざと見せつけられた。
夕方、くたくたになったぼくは事務所に戻り、「今日はよくがんばったな」と先輩社員にもねぎらわれ、ロッカー室に入った。携帯電話には兄からの数件の着信。イヤな予感がした。
「オヤジが、死んだんよ」
今日が入社初日であることを、父は知っていた。数日前に電話で話したからだ。
でも、その時は何も異変に気付かなかった。
この時ばかりは、虫の知らせが、なかったのだ。
いや、あったのかもしれない。今思うと、虫の知らせは連呼されていた。
あの家はひとりで暮らすにはあまりに広すぎる。小まめに電話こそしていた。だが、電話越しの父の声は気丈に振る舞うものの、寂しそうだった。それら一つひとつが、虫の知らせだったはずだ。
でもそれに気づかなかった、気づいてもスルーしていた。新しい街、新しい恋人、新しい仕事、東京での新生活に、ぼくは夢中だった。
その日のうちに、山口に戻った。
悲しかった。でも寂しくはなかった。
なぜなら、母の時からすでに、死者はぼくの中に入り込んでいるという感覚があったからだ。父も同じだった。
ただ、申し訳なかった。悲しみの涙が、通夜の時も、出棺の時も、止まらない。ぼくが、ぼくの中の父が、激しく泣いている。
入社初日に父の逝去。葬儀社の上司先輩たちは、だれもが「もう玉川はここには戻ってこないだろう」と思っていたのだそうだ。
ぼくは二週間後、東京に戻り、社長にこう言った。
「また明日からお世話になります。よろしくお願いいたします」
この日から、とむらいマンとしての人生が、始まった。
虫の知らせは無視するな
42歳になったぼくは、22歳のぼくにこう言ってあげたい。
「虫の知らせは、無視するな」
これはあなたにも言いたい。
毎日が忙しいのも分かる。大事なものを見失ってしまうのも分かる。
でも、虫が何かを知らせた時、一旦手を置くことの余裕を、持っていたほうがいい。でないと、取り返しがつかないことになるかもしれない。
何のために生きているのか。その核になるものを失ってしまった時の喪失感は、ことばでは言い表せない。
虫の知らせを受けたならば、電話でも、ラインでも、SNSの「いいね」でもいい。相手になにかリアクションをするべきだ。でないと、後悔ばかりがずっと残り続ける。
ありがたいことに、ぼくはもうすでに、亡き家族とともに生きている。死別を受け入れることができた。
とはいえ、大事な家族を看取ることなく亡くしてしまったのは、やっぱり取り返しがつかないことだった。
いまだって、ずっと、そう思っている。


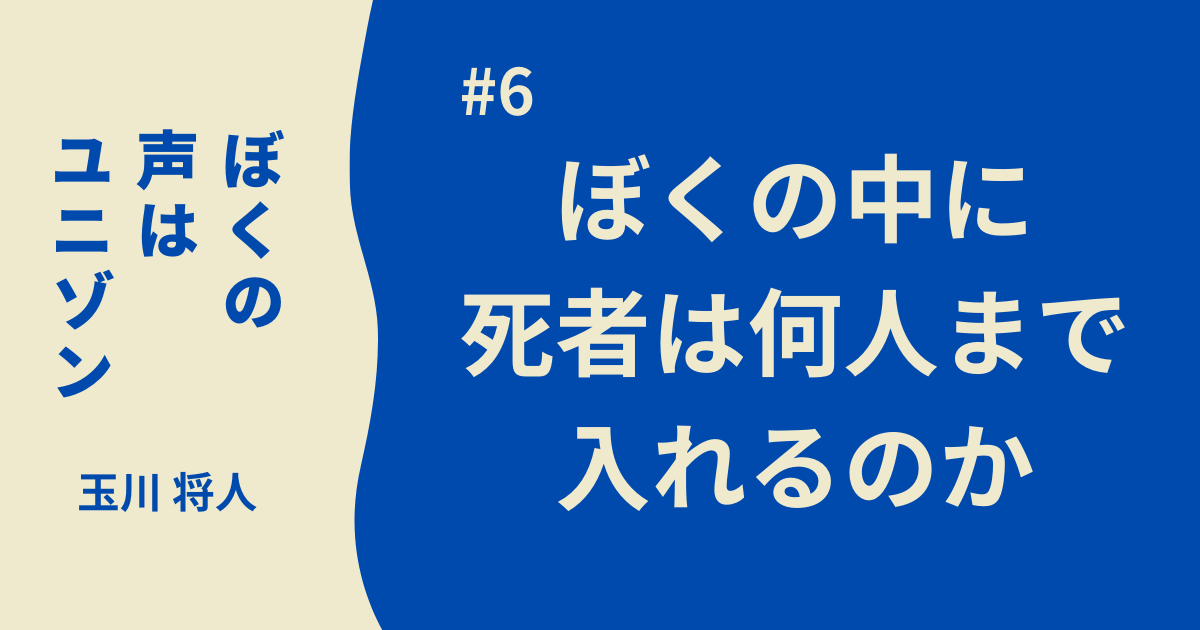

コメント