もうメタクソのボロクソに言われている戒名も
あながちバカにできないし。
こんにちは。とむらいマンです。
「寺離れ」「葬儀の簡素化」なんて言葉が言われて久しい昨今ですが、
その原因たるや、なにやら得体の知れない戒名というものが大きく横たわっていると思うのです。
「なんで死んだ人に名前をつけんにゃいけんの?」
「戒名料って、なんであんなごっつい高いん?」
もうメタクソのボロクソに言われている戒名ですが、
僕は、戒名はあながちバカにできないし、充分価値のあるものだと思ってます。
ただ、それを庶民に授けるお寺さんの言葉が足らないし、
庶民の側も死をなめているところがあると、思う。
僕たちは、戒名をなめすぎています。
戒名の力は絶大なのです。
だから僕は今日、この場を借りて、戒名の本質を語ろうと思うのです。
戒名は仏弟子の証 生者にも死者にも授けられる
戒名は”亡くなった人に授ける名前”というのが一般的に認識されてるとこじゃないでしょうか。
しかし、本当のところを言うと戒名とは、授戒した人に授けられる名前で、仏道を歩む出家者の証のようなものです。
なにも亡くなった人にだけではなく、生きている人にも授けられるのが本来の使い方。
このへん、もう説明がめんどいので、Wikipediaさんにお任せします。引用ドン!
戒名(かいみょう)は、仏教において受戒した者に与えられる名前である。仏門に入った証であり、戒律を守るしるしとして与えられる。
上座部仏教と大乗仏教の両方で行われており、多くの場合、出家修道者に対して授戒の師僧によって与えられる。
(中略)
また日本においては、死生観の変化により死後に成仏するという思想のもと、故人に戒名を授ける風習が生れた。死後の戒名は、特に日本において盛んに行われている。
俗名と戒名 瀬戸内寂聴さんの場合が分かりやすい
もっとも分かりやすい例を挙げるなら、瀬戸内寂聴さんという人がいますね。
彼女はもともと瀬戸内晴美という名の小説家でした。
そして天台宗で得度をして、僧侶としての名を寂聴としました。
「晴美」が俗名であるならば「寂聴」が戒名というわけです。
彼女は生きながらにして仏道に進んだ。
戒(僧侶としての守るべき戒律)を授けられ、名前を授けられたのです。
日本は、死後に成仏するという一種の信仰があるので、
死して仏と成る者に、戒名が授けられた。
これが、いまの戒名文化の大前提にあるということを、まずは頭に入れておきましょう。
ネットで見かける戒名の情報は、どれも俗っぽいものばかり
さて、ネットで「戒名」と検索すると出てくるのは
●葬儀屋さんのサイト
●葬儀系ブログのサイト
●お寺さんのサイト
…です。
葬儀屋さんや葬儀系ブログは、戒名のランクだとか、戒名料がいくらだとか、お布施を渡すタイミングだとか、お布施の表書きは何て書けばいいのかとか、まあほんとそういう俗っぽいことばかり。
一方、お寺さんのサイトというと、戒名は仏弟子の証なんですよと、本質的なところを語ってはいるのですが、そもそも受け手側が仏弟子になりたいと思ってないし、その価値を感じていないから、視点がお寺さんサイドに偏ってるばかり。
しかも戒名料には常に一種のバッシングがつきまとうので、お寺さんも高らかと戒名肯定論を言いにくい面もあるし。
そう、言葉が響いてこないんです!
なぜ人々にとって、戒名が必要なのか
だからこそ、今日僕は、ここで戒名についてその本質を語ろうと思ってます。
本質ですよ。本質。
戒名のランクとか、戒名料の相場とか、そんなのここではどうでもいい。
もっと手前の、もっと大事な話。
なぜ人々にとって、戒名が必要なのか!
について語るということです。
別に僕は僧侶じゃありません。
戒を誰かに授けたこともありませんし、授かったこともない俗人です。
だけど、お寺の周りで13年間働き続けているし、自分自身も立て続けに家族を亡くしたし、その時に家族みんなの戒名や法名をお寺から授かるという経験をしたし、37歳で5回それをしているのだから、まあ多い方だと自認します。
だから、それなりに語る資格はあるのじゃないかと思ってます。
さっき僕は戒名は「なにも亡くなった人にだけではなく、生きている人にも授けられるのです」と言いました。
ただ、ここでは出家者の生前戒名については省きます。
あえてみんなが批判するところの戒名、つまりは、お葬式ではじめて授かる戒名について語ろうと思うのです。
戒名の持つとっても大切な2つの役割
僕は戒名には2つの役割があると思ってます。
しかもこの2つは、僕たちがこの世界を幸せに生きていくための、とーーーっても大切な役割です。
戒名の役割のひとつは、
「あの人が、あの世でも幸せでいられますように」という願いを込めるため
もうひとつは、
「あの人はもう、この世の人じゃない」と受け入れるため
この2点に尽きるんです。
詳しく噛み砕いて解説します。
【役割1】あの世での幸せを祈るための戒名
戒名の大事な役割のひとつは、
「あの人が、あの世でも幸せでいられますように」という願いを込めるため
…です。くわしく語っていきますよ。
名前をつけることで個性を持つ
名前をつけるとはどういうことでしょうか。
たとえば両親は赤ん坊に名前を付けます。
そこにはこの可愛い子供が「こうあってほしい」「あーなってほしい」という親心としての願いが込められてますよね。
と同時に名前をもらうことで赤ん坊はその名前の人間として、主体性(=個性)を持つことになります。
名前を与えられることで、あの人でもこの人でもない世界でただ一人の自分という個性が浮き上がってきますし、親は子をこの世で唯一無二の存在にするのです。
名前ってのは、そういうものなのですよ。
戒名も同じです。
戒名はお坊さんが、あなたは「この戒を守って仏弟子として生きなさい」「こうした心持で死後の世界を安心して進みなさい」というような一つの想いを込めて授けます。
そして戒名を持つことで、死者も死者としての主体性(=個性)を持つわけです。
戒名を与えられることで、あの人でもこの人でもないあの世でただ一人の自分という個性が浮き上がってきますし、遺された家族は死者を唯一無二の存在にするのです。
死後の世界の立証なんてどうでもいい。大事なのはこの世から見た死者の姿
「死んでしまったら無に還る」「この世にいない奴なんて名前を授けてもしょうがない」
こういう論理はここでは通用しません。
たしかに死者は死んでしまったのですから主体性なんてあったもんじゃないでしょう。
あの世があるかないか、死後も人は生き続けるなんて、死の側から立証した人はこの世に一人もいません。
そんなことはどうでもいいのです。
大事なのは死者が死後の世界をどう生きているかではなく、「死者がきっと死後の世界を生きているはずだ」という、この世から見た死者の姿、これこそが大切なのです。
僕たちは死後の世界を知りません。
だけど死後もきっと死者たちの世界が広がっていて、死者はその世界を生きるんだというひとつの仮説のような物語が、僕たちの心を、亡き人を失ったことによる悲しみを癒してくれます。戒名はそのために授けられるのです。
死者の個性はやがて薄れ、33回忌で無に消えていく
余談ですが、「問い切り」という言葉をご存じですか?
「弔い上げ」なんてことばでも呼ばれていますが、死者の供養は33回忌で1つの完成を見るという考え方。
先祖の位牌は、33回忌を経て(地域によっては50回忌)、個別の位牌から「先祖代々」の位牌にまとめられていきます。
なぜ33回忌かというと、33年もすれば死者を供養する本人も死んでいくころだからです。
親を供養する子、そして孫と、世代が下っていくごとに、死者の記憶は薄れていき、やがては消えてなくなっていきます。
その消えてなくなるころが33年であり、「〇〇〇〇居士」という個別の先祖は、「先祖代々」という形でまとめられていくのです。
ちなみに、民俗学者の柳田国男は、日本では、死者の霊(荒魂:あらみたま)は49日で仏になり(和魂:にぎみたま)、33年で神になる(神霊=氏神)のだと言ってました。
古い先祖は、家の先祖から、共同体の古い先祖にまとめられ、「氏神様」として祀られていくのです。
僕たちが秋にバカみたいに「わっしょいわっしょい」と担いでは酔っぱらうあのお祭りは、古い先祖である氏神様との交感の場なのです(これについてはブログ記事『みんなの先祖をみんなで担ぐ秋祭り 神輿は重いからこそありがたい』をぜひ!)。
この日本人の死者供養システム。僕、マジ、すごいと思ってます!
このへんの日本人の死生観は、ブログ記事『位牌がたくさんあって困る! ご先祖様をまとめる便利な位牌をご紹介』をぜひ!
その中でも引用してますが、民俗学者の谷川健一さんが、「まさにそれっ!」てことを語ってらっしゃってます。引用、ドン!
生者は死者が自分にうるさく供養を要求するのが面倒くさいんですね。それで「問い切り」という現金な言い方をして死者を無名の魂に帰すんです。その前は戒名があるので、個人の匂いがしますけれど、いずれは無名の世界に帰っていく。つまり、仏から神になる。
谷川健一『日本人の魂のゆくえ』
【役割2】あの人の死という現実を受け入れるための戒名
さって、戒名のもうひとつの大切な役割がこちらです。
「あの人はもう、この世の人じゃない」と受け入れるため
これ一体どういうことでしょうか。ズズイっと続けていきますよ。
門を叩いて名前を授かるニッポン文化
さてみなさん。こんな疑問が湧きませんか?
遺された人間が悲しみを乗り越えるために、死を受け入れるために、死者は死後も生きているといことで名前を授ける。ではなぜ…
生前の名前ではダメなんすか?
はい。もっともですよね。
死者は死後も生きている。生きている、存在しているからそのものに名前を付ける。
その名前は、生前の名前じゃダメなの?
という疑問ね。
ダメなんですよ。
なぜ、ダメなのか?
ひとつには、仏教的な意味があります。
仏弟子は出家するわけでね。
父母のもとを飛び出していくわけです。
生前の名前というのは父母から授かった名前ですが、
そこを飛び出して仏道に進むことが出家です。
その門を叩いて新しい名前をもらうのは、なにも仏道だけではありません。
お相撲さんもそうですし、落語、歌舞伎、能とかいった芸能もそうですよね。
新しい師匠に仕えるものは、その師匠から名前を授かる文化というものが、そもそもわが国ニッポン文化の素地としてあるわけです。
ちなみにこれは家族間でも言えそうですよね。
お嫁さんや養子さんは、自分の姓を捨てて相手の姓を名乗りますよね。
女性の人が旦那さんの家に嫁いで、男性の人が婿養子に入って自分の苗字を教えて相手の姓を名乗ると同じように、仏門を叩いた人は、世俗の名前を捨てて、師匠から戒名を授かるのです。
ただ、これはあくまでも「死者=仏道」が供養につながるという前提のお話です。
極めて仏教的なお話なのですが、もっと手前の、根源的な理由があると思うんですよ。
どんどん続きます。
生者と死者と名前を分ける 僕たちは住む世界が違うんだ!
死者に授ける名前が生前の名前を使わずに戒名にする最大の理由は、さっきも言いましたが、
「あの人はもう、この世の人じゃない」という事実を受け入れるため
つまり、住む世界が違うんです。
お葬式のさまざまな儀礼、
枕元の屏風をさかさにして飾るとか
衣服を左右逆に着せるとか、
お湯は逆さにして作る(水入れてお湯で割る)とか、
愛用していたお茶碗をパリンと割るとか、
すべて、自分たちと死者が違う世界の生き物であることを認識させるための儀礼です。
では、どうしてそこまで死者と自分たちを区別させるのか。
それは、僕たちが死別の悲しみを乗り越えて力強く生きていくためであり、そのためには死者への未練を残さないためです。
だからこそ、死者は、生前の名前を捨てて、死者の名前を名乗るのです。
そうしないと、遺された人たちの心の中で未練ばかりがうじうじうじうじとうごめきわまってしまうばかり。
彼は間違いなくあの世で元気に生きているけど、私たちと同じ世界には生きていないんだ。
あの人は死んだんだ。
そう認識することが大事なんです。
そして、あの世とこの世は違うから、
あの世を生きる人の名前をこの世の人は授けられません。
あの世とこの世を媒介する存在、お坊さんだけが、それが可能なのです。
死者に名前を授けることで、僕たちは死者に個性を与え、その大切な人のことを想って、安寧を祈り念じます。
【まとめ】戒名は、遺された僕たちが力強く生きていけるためのもの
このブログ、5000字超えました。
ちょっとわけ分かんない人もいると思うんで、まとめますね。
●戒名は、そもそも仏弟子に授けられる名前のこと
↓
●日本では死後に成仏するという考え方から死者に授戒するという風習が生まれる
↓
●遺された側は、「あの人はあの世でも生きている」と考える。存在が生き続ける以上、名前を授けて、個性を与える
↓
●しかもその名前は生前のものではなく、死者としての名前。それを授けることで、あの世とこの世は違う世界で、住んでる場所が違うんだ、と自覚する
↓
●故人の死という事実を受けとめ、乗る超えることで、幸せに、力強く生きていける
ということです。OKですか?
【最後に】戒名の問題と戒名料の問題は、厳密に区別すべきだ!
以上、戒名がどうして僕らにとって大事なものなのかについてバババババっと、勢い半分確信半分で語りました。
論理的に破綻してるところはないと思うんですが、
「ふーん」
「んで」
「だから」
というような冷笑混じりな一般ピーポーの意見もあるでしょうし、
「おめえ勝手に戒名の解釈変えてんじゃねー」
と怒りの仏教者側の意見もあるでしょう。
だけど、戒名の根底には、人間という生き物は亡き人の死後の行方を案じてしまう習性を持っているというのは、疑いの余地がないんじゃないでしょうか。
ちなみにですね。
僕は今日、戒名について話をしたのであって、
戒名料の話はしていません!
「戒名いらない」「戒名きらい!」の声の心の中には、
●死後の成仏という仏教の教義が信じられない!
●戒名料の金額が法外すぎていや!
このどちらだと思うのですが、ここを明確にしなければなりません。
前者であればしょうがないです。
他の宗教、あるいは唯物論的に生きていかれたらよいと思います。
もしも後者で、戒名にまつわるお金に不信感を持っている人がいるならば、
無料で戒名を授けるお坊さんはたくさんいる、ということを付け加えておきます。
「金払ったら弟子入りしてやる」というものではないんです、戒名ってのは。(そんなこと言うのは上納金制度を敷く立川談志くらいか…)
ちなみにですね、
この戒名とお金の問題は仏教側から解決していかなければならない大問題です。
なんだかんだで江戸幕府が敷いた檀家制度という甘い汁に未だによっかかっているお寺たちは、
そろそろ自分たちの足で立ち、自分たちの声で伝え、
自力で戒名の大切さを伝えた上でそれを対価にしていかなければならないですよ。
行基や空也や重源や忍性をはじめとするさまざまな勧進聖たちのように、
自力で庶民を救済し、そして対価をいただく努力を。
がんばれ! 日本仏教!
でないと、この国の死生観が、どんどん脆弱していくぞ!
とむらいマン
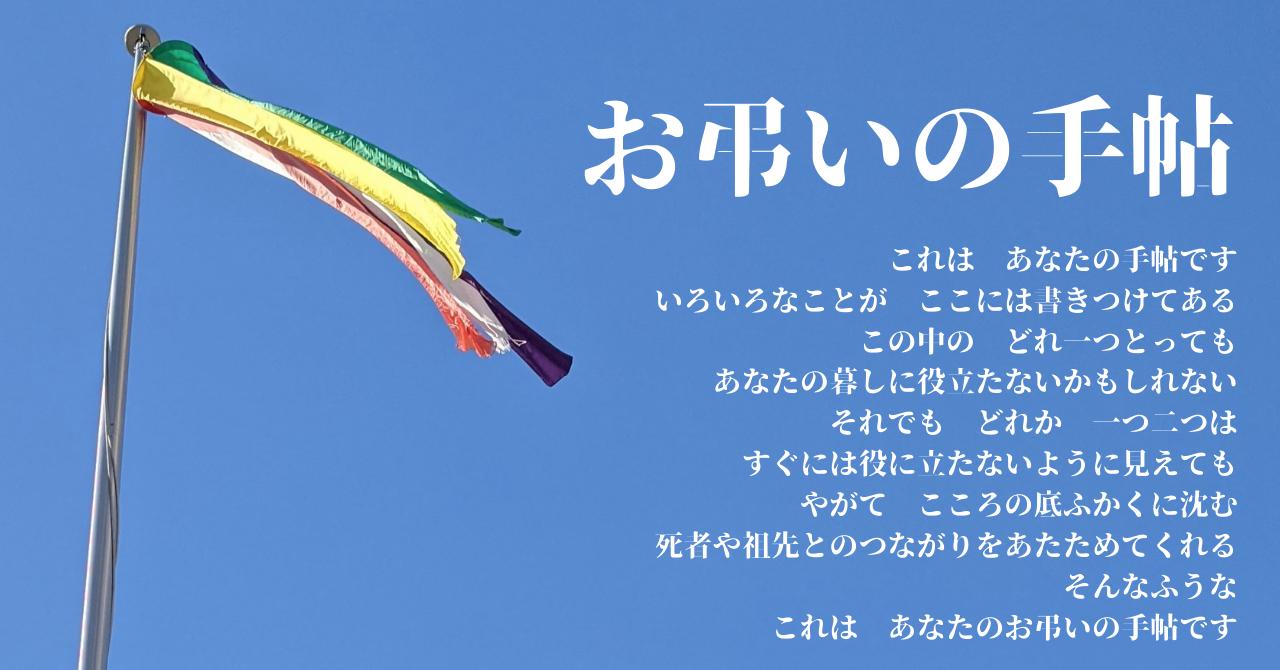
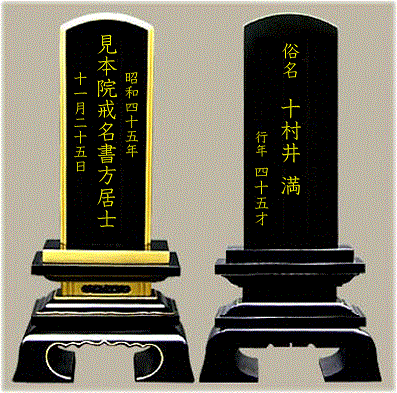


コメント